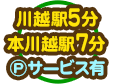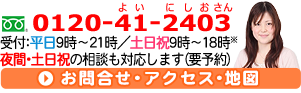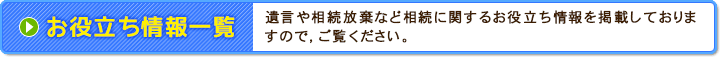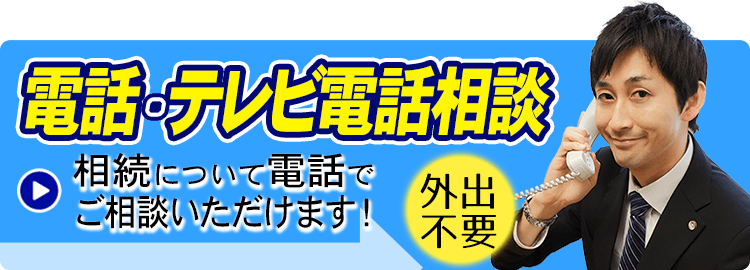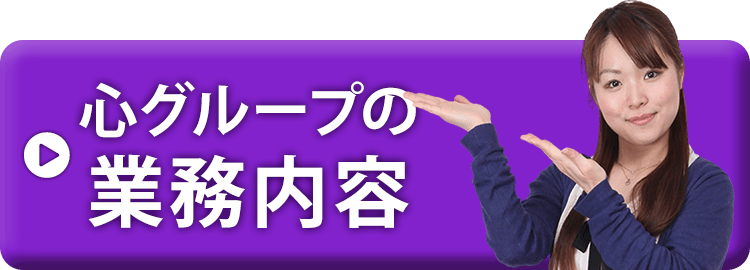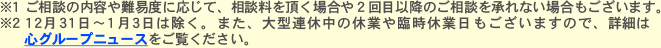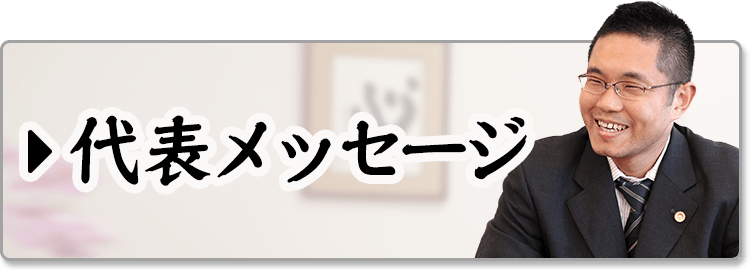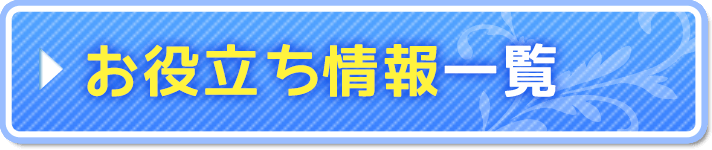相続した建物が未登記の場合のQ&A
未登記建物が他にもないか調査するにはどうすればよいですか?
被相続人の住居に配送される固定資産税の課税明細書を確認するか、建物の所在している各市町村で取得することができる「名寄帳」で確認することができます。
課税明細書や名寄帳に記載されている建物について、「家屋番号」の欄が空欄になっている場合には、未登記物件であると判断することができます。
未登記建物を相続する場合には、登記を行わなければならないのでしょうか?
未登記建物を相続した場合には、登記を行うべきでしょう。
通常、建物を新築した場合、所有者は、不動産を取得した日から1か月以内に登記の申請を行わなければならないとされており、これに違反した場合には10万円以下の過料が課される(不動産登記法164条)こととされています。
そして、今回はその義務に違反していた建物を相続するため、10万円以下の過料が課される地位も一緒に相続することとなります。
そのため、リスクを負わないためにも未登記建物を相続した場合には、登記を行う方が良いです。
未登記建物でも10万円の過料が実際に課された例は少ないという記事を見たのですが、それでも登記しなければならないのでしょうか?
未登記建物を登記しないリスクは他にもあります。
- ① 土地の固定資産税が高くなる可能性がある
-
通常、建物が建っている土地の価値よりも更地の価値の方が高いため、税金の計算上、建物がある土地の固定資産税は、更地と比べて最大で6分の1、同様に都市計画税は最大で3分の1まで減額されます。
各市町村が建物の存在を確認するのは、主に登記であることから、未登記のまま放置していた場合には、この減税措置が適用されていない可能性があります。
- ② ローンが組めない
-
未登記の建物には、抵当権を設定することができないため、新たに借入れを行う際に、ローンの審査を通過できない可能性があります。
- ③ 土地、建物を売却できない
-
未登記の建物では、正確に所有者が分からないため、売却を行うことが困難な場合が多いです。
また、建物を売却できない以上、土地も売却できないことになってしまうため注意が必要です。
これらのリスクを総合的に勘案すると、未登記建物を放置するよりも、登記を行った方が無難であるといえます。
また、令和6年度から相続登記が義務化されていることとの関係でも、国が未登記建物の対策に本格的に動き出しているとみることができるため、今後も過料が課されないと楽観することはできないと思われます。
未登記建物の相続手続きはどのように行うのでしょうか?
未登記の建物といっても、通常の相続手続きとほとんど同じ手続きを行っていきます。
- ① 遺言書の有無の確認
-
遺言書が作成されている場合には、その内容にしたがって相続を行います。
また、遺言書の作成が無い場合には、遺産分割協議書を作成して、その所有者を確定します。
- ② 市町村役場への所有者変更の届け出
-
各市町村役場では、固定資産税の課税の関係上、誰が未登記建物の所有者であるかを確認しています。
そのため、①で作成した遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書を提出して所有者が変更されたことを届け出る必要があります。
- ③ (未登記建物のままにしない場合)表題登記の申請、所有権保存登記の申請
-
土地家屋調査士に依頼し、表題登記を行う必要があります。
表題登記が完了した後、司法書士に依頼し、所有権保存登記を行うことで、所有権移転の手続きが完了します。