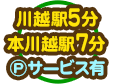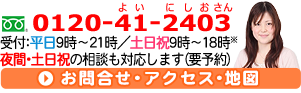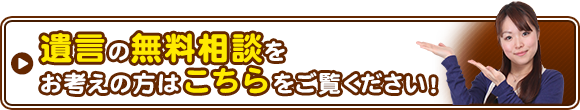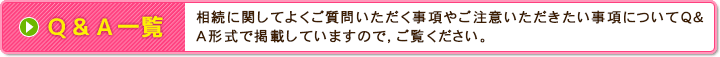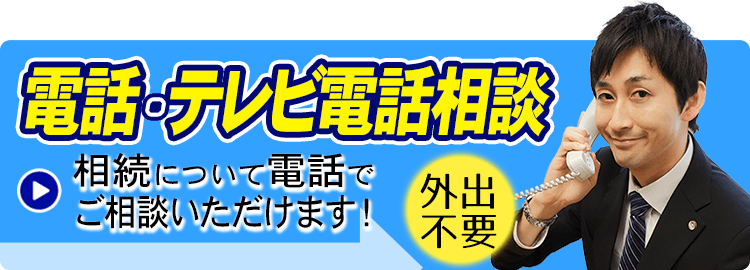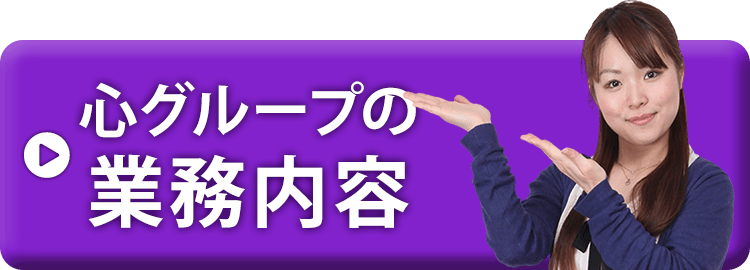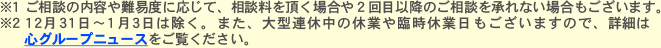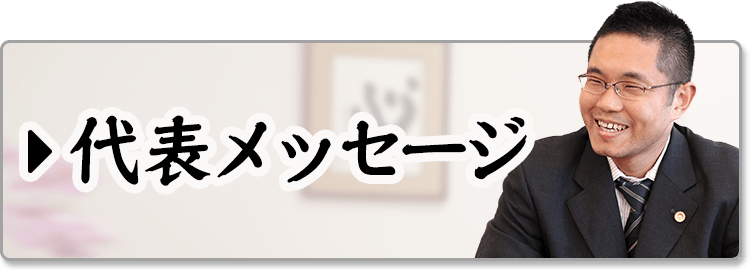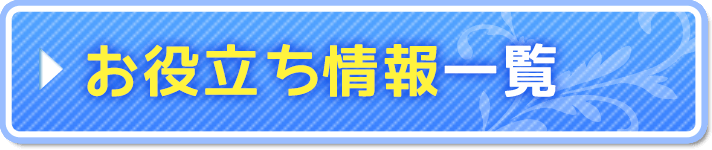遺言の種類とそれぞれの特徴
1 遺言の種類
遺言は、被相続人が自分の死後に自己の財産の行き先を決めるものです。
自己の遺産の行き先をすべて遺言に定めれば、遺産分割協議が不要になりますので、死後の相続人のことを考えれば、適切に遺言書を作成することは重要なこととなります。
遺言の種類は、大きく分けて、①普通方式によるもの、②特別方式によるものがあります。
特別方式による遺言としては、死亡の危急に迫った者が行う死亡危急者遺言などがありますが、普通方式に比べて数がかなり少ないものとなりますので、特別方式の遺言についてはここでは割愛させていただきます。
普通方式による遺言は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言がありますが、秘密証書遺言の利用数は極めて少ないといわれていますので、以下では、①自筆証書遺言、②公正証書遺言について説明いたします。
2 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、自分で遺言の内容の全文と日付および氏名を書いて、これに押印して作成する遺言です。
従来は、遺産の目録部分も含めて全文を自書しなければならなかったのですが、平成30年相続法改正により、自筆証書遺言に添付する遺産や遺贈の対象となる財産の目録については自書が不要となりました。
ただし、そのような自書されていない目録の場合には、その目録のページに署名し、印を押す必要があります。
自筆証書遺言の場合、原則として家庭裁判所に対する検認手続きが必要となります。
自筆証書遺言の場合は、遺言書が偽造・変造されるリスクや、保管者が遺言書を紛失・隠匿するリスク、法定の様式を満たさないため遺言書自体が無効となるリスクなどがありえます。
もっとも、現在は、法務局で自筆証書遺言書を保管してくれる遺言書保管制度があるため、遺言書が偽造・変造されるリスクや、遺言書紛失等のリスクへの対応が可能とはなっています。
また、この制度によれば、家庭裁判所への検認手続きは不要となります。
3 公正証書遺言
公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言を作成する方式の遺言です。
この遺言書は、公証人を通じて作成し、また、作成した遺言書の原本は公証役場で保管するため、遺言書が偽造・変造されるリスクや、遺言書紛失のおそれがなく、公証役場を通じて、遺言の有無が検索できるというメリットもあります。
また、元裁判官出身等の法律実務家経験を有する公証人が内容を確認するため、内容的に適正な遺言ができ、方式不備による無効の危険性も少ないというメリットがあります。
他方で、公正証書遺言は、公証人が関与するため、①自筆証書遺言の場合より時間・費用がかかる、②本人確認書類や実印、遺産の根拠資料等を準備する必要があるというデメリットがあります。
4 自筆証書遺言書と公正証書遺言書のどちらがいいのか
自筆証書遺言書は手軽に、また費用があまりかからずに作成できるという大きなメリットはあります。
しかしながら、自筆証書遺言書は、偽造・変造のリスクや、遺言能力等で遺言の効力自体が争われるリスクが公正証書遺言書の場合と比較して大きいと言わざるを得ないと思います。
遺言の作成の趣旨が、その後に残される相続人等に紛争を生じさせないで、自己の遺産を承継してほしいということにあるのであれば、自筆証書遺言に比べて費用は掛かりますが、紛争リスクが少なくなる公正証書遺言書が望ましいと思います。
それでも、自筆証書遺言を作成しなければならない事情がある場合には、後日の紛争を極力回避するべく、方式不備がないように徹底し、遺言の内容も一義的かつ明確なものとし、その上で遺言書保管制度を利用する等、種々の工夫をすることが望ましいと思います。
せっかく遺言を作成しようとされるのであれば、後日の紛争が残らないように、自筆証書遺言、公正証書遺言を問わず、どのような遺言書を作成したらよいのかという内容も含めて、専門家にご相談いただき、自己の遺志の実現を図られてはと思います。